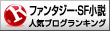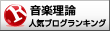第25回-音束と機能
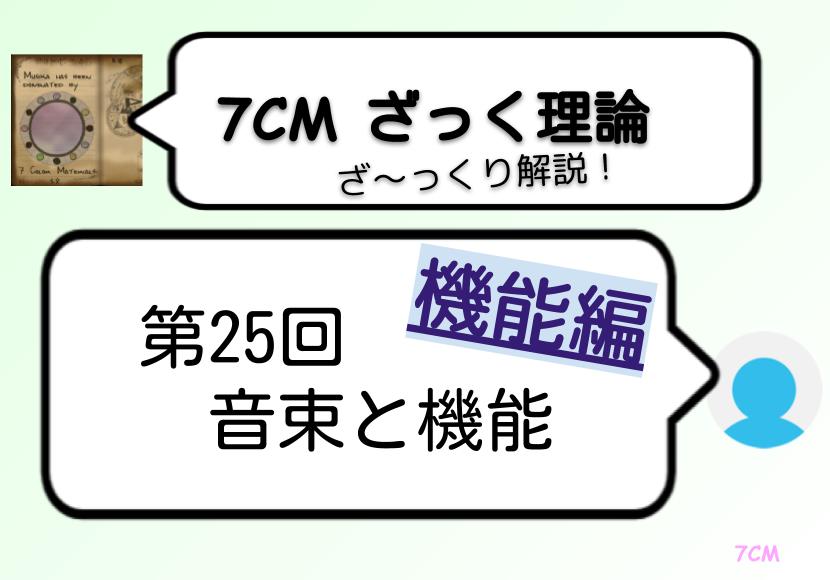
ざっくり機能編-目次
- [第21回] ベース機能
- [第22回] 調性内引力
- [第23回] 7CMの機能
- [第24回] 平行と多層
- [第25回] 音束と機能
- [第26回] 音の束ね方
- [第27回] 複機能状態
- [第28回] 非3度堆積束
- [第29回] 他7CMの例
- [第30回] 折れ線手法
前回までは、
・ベース音は機能を持つ
・機能は音の間の引力で定義される
・機能はTDLSの種類がある
とかとか、単音が持つ機能(単音機能性)について見て来たね。ここからはお待ちかね?の和音についてだよ。
音の束
7CM理論では和音・コードのことを束って呼ぶの。複数の音を束ねるからなの。
束ねる?重ねるとかじゃなくって?
束ねると表現したのには理由があって、ここから先ではこの複数の音達をまとめて1つの単音にみなすのね。これを見なし単音って言うのね。
複数の音をまとめて1つの音にみなしたものを、みなし単音という
前回までにベース単音は機能を持つってみてきたよね。ここからは、音を束ねたみなし単音が同様に機能を持つって考えるの。
Cコード{ド、ミ、ソ}の3音をまとめてド機能を持つ、みたいな感じ?
そのとおりよ。束ね方も多伎にわたるから前回までのベース単音よりも細かくなってくわ。
機能の本質部分
でもなんでわざわざ単音に見なすの?
まず、シンプルに単音で考えてその先細かいことをプラスアルファで考えた方が解りやすいってこと。例えば
・FM7(9) – G7(♭9)omit5 – Cadd9
っていう進行があったとして、これを
・F – G – C
って演奏することない?
あるある。簡単にして弾くってのは結構するよ。
その簡単にするっていうのは大まかに言うとコードを
・3or4和音 + それ以外
に分解して前者だけで演奏するってことよね。
そうだね。繊細さは変わってくるけど、進行感は変わらないね。
進行感っていう意味で言うとベース一本にしても変わらないんじゃない?もちろん明るさとか華やかさは失っちゃうけどね。
確かにベース一本で歌っている人もいるし、彩り感はなくとも機能的なものは成り立ってそうだね。
7CM理論では
見なし単音(機能) + 束ね方(感触)
って形で機能を見るの。ベース域に音があればだいたいはそれが見なし単音になるわ。
そして2点目としては、コードの型による評価は機能としては本質的ではないっていう点。
型ってメジャーコードとかマイナーコードとかの形ってことだよね。メジャーは明るいしマイナーは暗いし、特徴あるから機能にも影響しそうだけど。
メジャーコードは明るいっていうのは本当?
in Fmの状況下を考えてみて。Cmは暗いよね。じゃーここでCメジャーコードだったら?Cはどぎつく暗いイメージよね。FHmのドミナントだからね。
その先どこにいきたいかという機能は、コードの型ではなくベース単音や束が握っている。この場合はド機能ね。
じゃーコードの型は意味をなさないの?
そんなことないよ。それは束ね方として「単音機能の主張の仕方」「感触」を担うの。
難しいなぁ。
ベース=長和音@機能
この話は次回お話するとして、ここではより完璧なものを紹介するわ。それは・・・
長和音!これはとても強固にまとまって単音の機能を主張するわ。
メジャーコード?
低音域の単音と中高音域の長和音
ベースを聞いてるとき、音楽を聴いている人の心はベースの倍音にも包まれているの。
倍音って聞いたことあるね。楽器ってその基音の周波数の整数倍の音を含んでるんだっけ。
えぇ。そして倍音は整数が小さい倍数の方が生じやすい。つまり2倍、3倍、・・・の順ね。たとえばベースでC音が鳴ってる場合、
1倍音:ド
2倍音:ド
3倍音:ソ
4倍音:ド
5倍音:ミ
6倍音:ソ
・
・
・
って倍音列が出来上がるの。

あれ!?3~4倍音まででパワーコード、5~6倍音まで見るとメジャーコードが出来上がってる?
気付いたわね、そのとおり!逆にいうと
・中高音域でメジャーコード(ドミソ)を鳴らすと、ベース音(ド)を鳴らしているときと同じような成分で心を包み込む
ってことがわかるね。つまり
・メジャーコードは単音性が強い(ベースと同等の機能を持つ)
って言えそうね。倍音づてにベースを想起させてその単音機能を発揮する。
あ!だからドミソとベースのドは同じような機能になるってことだね。なるほどー。
あれ、じゃーマイナーコードはどうなるの?

マイナーコードは、4倍音まではベースの倍音と同じだから単音性は強い部類なんだけど、5倍音の長3度(ミ)を和音内の短3度(ミ♭)が否定するから「ベース音(ド)だぞ!」って主張を弱める、すなわち機能を減速的に緩めるの。つまりメジャーコードよりも機能性は弱くなる。
極端な話をすると、メジャーコード以外の型は、単音機能性においてはメジャーコードの劣化版になるの。
あ、だからメジャーコードが完璧って言ったんだね。一番単音性が強いと。
マイナーコードが暗く感じることが多いのも長3度に届かなかったってことと関係するのかな。
えぇ。これは機能とは別のお話(光彩)になるけど、ブルーノート然り到達しないことの哀愁もあるし、細かにいえば単音機能がなす小調性上の光彩・主明度を下げたからって話ね。これはまたの機会に。
次回
ベース域の単音は倍音で高音域にメジャーコードを形成し、逆に中高音域のメジャーコードは基音となるベース音を想起させて機能を持つってことが分かったね。
じゃーメジャーコード以外は…っていう束ね方のお話を次回から見ていくよ!