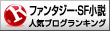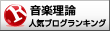第14回-自然の重力
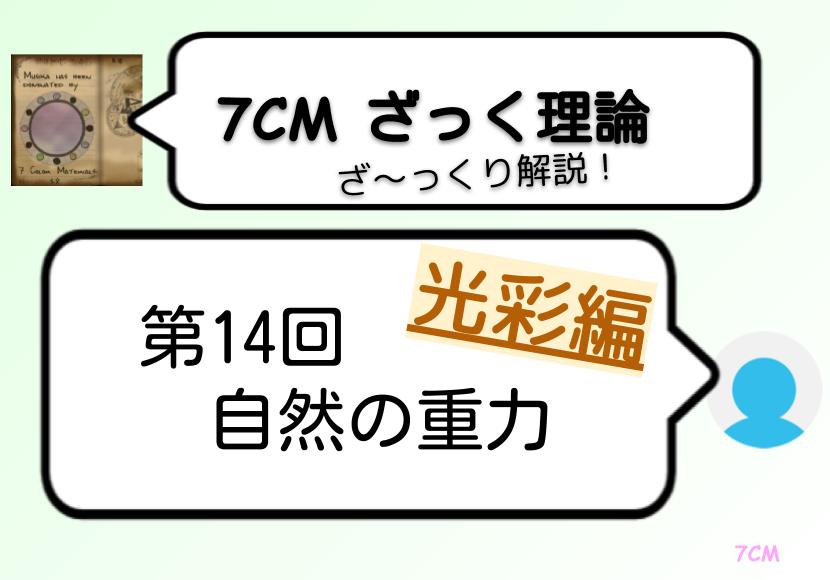
ざっくり光彩編-目次
- [第11回] 光彩の概要
- [第12回] 自然な光彩
- [第13回] 光彩残り香
- [第14回] 自然の重力
- [第15回] m系代表型
- [第16回] SDmの出身
- [第17回] M系代表型
- [第18回] モード7CM
- [第19回] 応用:D表記
- [第20回] 光彩まとめ
前回の例を振り返ると、
・in CNM={ド、レ、ミ、ファ、ソ、ラ、シ}
の曲調で、
・コード:D7={レ、ファ♯、ラ、ド}
が出てきて、
・次の7CM={ド、レ、ミ、ファ♯、ソ、ラ、シ}
に変化したね。
そしてこの状態は一定時間継続する。

この2小節目だね。そしてこの状態やファ♯などの具体的な音のことを残り香って呼ぶんだったね。
ところで、一定期間ってどういうこと?
自然調性重力
自然調性であるNM、Nmはね、数多ある7CMの中でも一番安定しているの。そして安定しているということは、すなわち心がそれを求めてる状態にあるの。
簡単に言っちゃえば、自然調性以外の調性の中にいるとき、心のどこかでは近しいNMあるいはNmを求めちゃう、そんな重力のようなものが自然調性にはあるの。
自然調性以外の調性にいるとき、近しいNMあるいはNmを心は求める
へぇ。あ、確かにさっきの例で3小節目はファがナチュラルに戻ってたね。そこに違和感はなかった。そういうことか。なんでそんなことになるんだろう?

そこには調性の調和だとかそこからの乖離だとか色々あるんだけどね、その辺は7CM理論の方を読んでもらうとして、ここではこの事実と、自然調性から外れた音が乖離音として特徴を持つってことを憶えてね。
例で言うとファ♯が自然調性から外れた音ってことだね。
そのとおりよ。2小節目で凄くキラッキラな響きを引き連れてきたよね。これまでの雰囲気をギラっと変えたような。
あーなるほど。確かにそこまでの雰囲気を少し変化させた特徴的な音だね。
そのあとの展開がどうなるか、それは
・ファ♯のある世界
でもいいし
・ファに戻った世界
でもいい。重要なのは、
・残り香のファ♯ VS 元の自然調性 ファ
の間を心が揺らぐということ。
ファに戻った世界は聴いたね。ファ♯の例も聴きたいな。
3小節目でのファをファ♯にした例を聴いてみてね。

うーん、個人的には気になっちゃう。でもキラキラな曲調だって考えてこれもありかなぁ。繰り返し聴いてるとなれてきた感じがする。ただ自然ではないし、やっぱり特徴的な感じだよね。
なるほど、なしよりのありくらいの感想かな?心の期待していた順位としては
1.ファに戻った世界
2.ファ♯のままの世界
っていう順かな。
そうだねー。
・・・
あ!だから残り香は一定期間って話なんだね。
・2小節目:ファ♯優勢!
・3小節目:ファ>ファ♯
心の期待値はこんな感じで、ファ♯の残り香が小さくなったって感じだった。
そうね。ちょっと楽譜に細工して可視化してみるね。
・2小節目でファ♯1回パターン
・3小節目でCNM復帰パターン
・3小節目でまたファ♯パターン
青がCNM、黄色がファ♯のある調性だとして、残り香がうっすら消えていく状態を可視化すると次の感じかな。

なるほど!まず、どのケースも2小節目でキラっとしてた雰囲気を引き連れて来るね。
1ケース目はその後その特徴的な音(ファ♯)が出て来ないから曖昧に元の調性に戻ってる。
2ケース目は明示的にファで元の調性に戻ってることが実感できて、結果的にこのときにはファ♯の残り香が消えかけてたんだなってわかる。
3ケース目は残り香を消さないような駄目押しのファ♯な感じだね。
ちなみにこのファ♯状態のギラつきってなんていう7CMでどんな光彩になるの・・・?
その辺は次回以降ね!
次回
次回からは7CMのよく使用される代表的な型について説明するね。まずはマイナー系7CM代表型よ。それこそ一般的な音楽理論でもマイナー系として固有名称持つような有名なものから紹介するね。