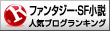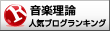第12回-自然な光彩

ざっくり光彩編-目次
- [第11回] 光彩の概要
- [第12回] 自然な光彩
- [第13回] 光彩残り香
- [第14回] 自然の重力
- [第15回] m系代表型
- [第16回] SDmの出身
- [第17回] M系代表型
- [第18回] モード7CM
- [第19回] 応用:D表記
- [第20回] 光彩まとめ
簡易度数類たちの役割は一旦ふんわりわかったけど、具体的にはどういう風に役割が効いてくるの?
音の光彩はね、高いほど強く/低いほど弱くなるの。
えっと、主明度だったら高い方が明るくって低い方が暗いってことかな。ハ長調でミがミ♭になると…おぉ、なるほど暗くなるね!そういうことなんだね。
ピンと来てるわね。前回最後に話をした主光彩を覚えているかしら。主光彩が3つとも全部下がった状態を考えるとわかりやすいね。
ハ長調(Cメジャーキー)は
ドレミファソラシ
これの主光彩の3つとも下がると、
主明度:ミ→ミ♭
主彩度:ラ→ラ♭
主輝度:シ→シ♭
となって
ドレミ♭ファソラ♭シ♭、つまり
ハ短調(Cマイナーキー)になるよね。
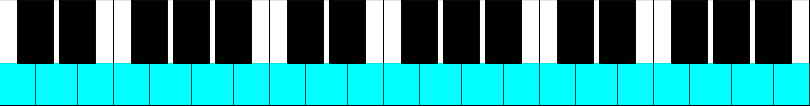
主光彩の3つとも下がると次のようになるの。
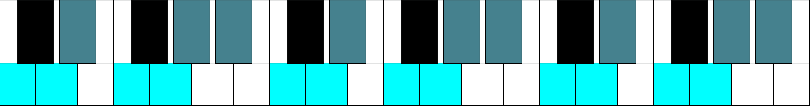
ははぁ、
・明るさ
・鮮やかさ
・ぎらつき
が押さえられた感じ、確かにそういわれてみればそう感じるかも。
可視化するとこの2つはこうなるわ。
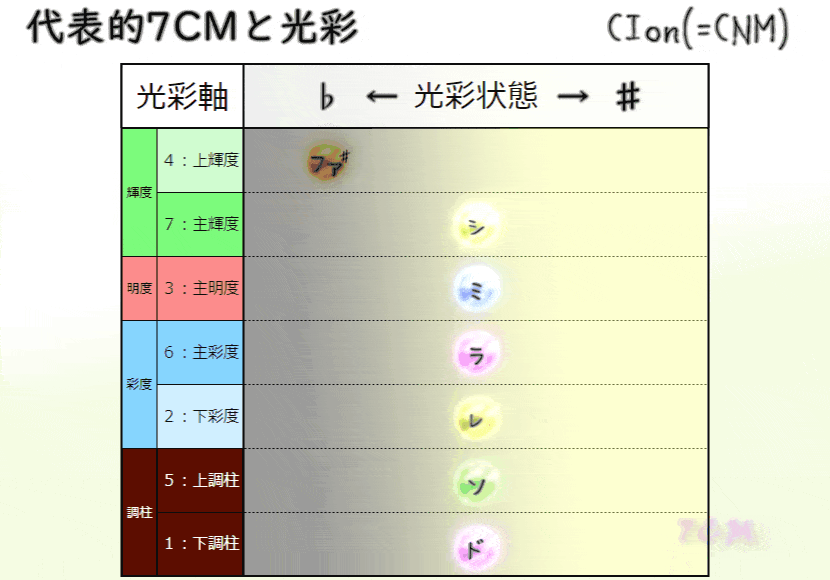
この主光彩が上がっている方を
・NM(ナチュラルメジャー)
と呼んで、主光彩が下がっている方を
・Nm(ナチュラルマイナー)
と呼ぶの。ド(C)が中心となる7CMは、それぞれ
・CNM
・CNm
って表して、音楽世界がこの7CMになってる状態のことを
・in CNM
・in CNm
のように「in 〇〇」って表記するの。
長調で臨時記号(≠調号)がつかない音の間隔をナチュラルメジャーと呼び、NMと表記する
ド、レ、ミ、ファ、ソ、ラ、シはCNM
短調で臨時記号(≠調号)がつかない音の間隔をナチュラルマイナーと呼び、Nmと表記する
ド、レ、ミ♭、ファ、ソ、ラ♭、シ♭はCNm
ラ、シ、ド、レ、ミ、ファ、ソはANm
ある7CM状態にあることを in 〇〇と表す
ナチュラルメジャー、ナチュラルマイナー…
自然な長調、自然な短調みたいな感じかな?
そのとおりよ。これらは自然調性と呼んで他の7CMを評価する基準になる7CMなの。
NMとNmを自然調性と呼ぶ
自然調性は他の7CMを評価する基準となる
基準となる…?
そうね、他の代表的な7CMを紹介する前にまずはその辺のお話をしましょうか。
次回
次回は『光彩残り香』よ。音が心の中にしみつく残り香という事象について説明するね。